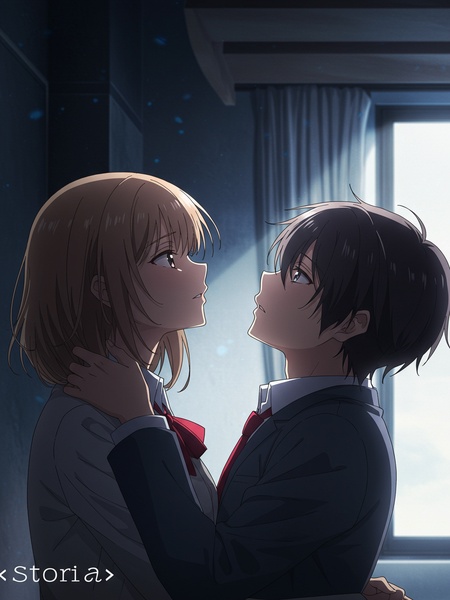第6話:本当の絆
6
誰かがそう言うと、他のゲストも乗っかる。
「隼人兄さん、幸せ者だね。小お嬢様に溺愛されて〜」
「隼人兄さんの人生はまるでおとぎ話みたい。羨ましすぎる。」
「私も隼人兄さんみたいに小お嬢様の彼女がほしいよ〜」
ヴィラの廊下は、和やかな空気に包まれていた。誰かが「これはSNSでまたバズるな」と囁く。
隼人は少し驚いた様子で、指をいじりながら顔を伏せた。「ああ、もう、やめてよ。ちょっと見てくるね。」
ディレクターが「みんなで見に行こう」と提案。
全員でヴィラを出ると、スタッフがアラスカン・マラミュートのリードを持って立っていた。
犬の大きさに、ゲストたちは思わず歓声をあげる。毛並みはまるで雪のように白く、目は澄んでいて、存在感抜群だった。
私のスマホに紗良からLINEメッセージが届く。
「旦那様、おじいちゃんが急に会議を入れたの。コマツのことお願いね。夜迎えに行くから。」
私はまぶたをピクッとさせて返信した。
「今、生放送中なんだけど。なんでコマツをここに送ったんだ?」
「何を企んでるか知ってるぞ。今すぐ連れて帰れ。」
紗良は写真を送ってきた。「今オフィスにいるよ。」
証拠写真には高級会議室と、村上家の家紋が入ったカップが写っていた。
私はスマホをロックし、深呼吸した。
数分でどうやってオフィスに行ったんだ?
隼人は辺りを見回した。「犬だけ?」
「村上社長は会社に行くから、犬はパパに渡してって言われたんです。」
そう言ってスタッフはリードを隼人に手渡した。
アラスカンの毛はふさふさで艶やか、風に揺れて美しい。ゲストたちは思わず撫でたくなる。
「隼人兄さんと小お嬢様が飼ってる犬、名前は?」
そう聞いたのは、村上メディア所属の新人俳優・佐伯駿。頭の回転が早いことで有名だ。
隼人は突然耳を赤くした。「えっと……どう言えばいいかな……」
7
それを見て皆がからかい始めた。
「わあ、隼人兄さん照れてる。ますます名前が気になる!」
「絶対隼人兄さんにちなんだ名前でしょ。」
みんなに煽られ、隼人は咳払いして答えた。
「仕方ないな。彼女がどうしても“はやはや”って名付けたんだ。なんか響きが可愛いからって。」
佐伯駿は羨ましそうに顔をしかめた。「うう、また犬カップルの惚気を見せられた。もう番組やってられないよ。」
「小お嬢様は隼人が大好き。犬の名前まで隼人中心なんて。」
「犬カップルばかりで、独り身には辛すぎる……」
「アラスカン、めっちゃ美しい。隼人に溺愛されてるんだろうな。」
私は思わず口元を引きつらせた。
コマツは自分の名前を変えられて納得してるのか?
小声で「コマツ……お前、今どんな気持ちなんだ」とつぶやいてしまう。
目ざといネット民が私の表情を見逃さず、すぐコメントが飛んできた。
「橘悠真、何その顔?めっちゃ嫉妬してるじゃん。」
「嫉妬?隼人の発言が痛すぎて、無言になるのも当然だろ。」
「橘悠真はきっと小お嬢様を隼人から奪おうと企んでる。」
「夢見てろよ。小お嬢様が好きなのは隼人だけ。どこの犬猫でも勝てるわけない。」
ネット民のノリの良さに、つい画面をスクロールしすぎてしまう。スマホを持つ手が熱くなった。
隼人は佐伯駿の言葉に満面の笑みで、アラスカンをヴィラへ連れて行こうとした。
だが犬はその場に座り込み、動こうとしない。
彼は辺りを見回し、誰かを探しているようだった。
「パパ、どこ〜?匂いがするよ。」
隼人はカメラに向かって気まずそうに笑った。「はやはや、行こう。」
アラスカンはぷいっと顔を背け、まるで紗良のようなツンとした態度。
それを見て、私は思わず笑ってしまった。
コマツは私の声を聞くと、隼人のリードを振り切ろうとした。尻尾を千切れそうなくらい振って、前足で私の方にちょんちょんと跳ねる。
「さすが隼人と小お嬢様が育てた犬!あの顔のそむけ方、可愛すぎて死にそう!」
「隼人ファン、見てよ。犬は隼人を全然見てないよ?」
「爆笑。隼人ファン、集合。小お嬢様の犬は隼人に興味なし!」
「アンチが適当言ってるだけ。犬が隼人になつかないなら、誰になつくの?隼人こそ小お嬢様の本命彼氏だよ。」
「小お嬢様はまだ認めてないのに、本命彼氏扱いは早すぎ。笑い話になるぞ。」
「正直、アラスカンは橘悠真に行きたがってる気がする。」
「ぷっ。もし隼人があの嫌な橘悠真を好きなら、逆立ちして納豆ご飯食うわ。」
そのコメントを見て、私はニヤリと笑い、コマツに手を振った。「コマツ、おいで。」
ヴィラの中庭に、初夏の風がそよいでいた。コマツの耳がぴくりと動き、私の方をじっと見つめる。何も言わなくても、彼の目が「早く会いたかったよ」と語っている気がした。初夏の風がカーテンを揺らし、遠くで電車の音が静かに響いていた。周囲の視線も忘れ、思わず小さく手を振り返した。
続きはモバイルアプリでお読みください。
進捗は自動同期 · 無料で読書 · オフライン対応