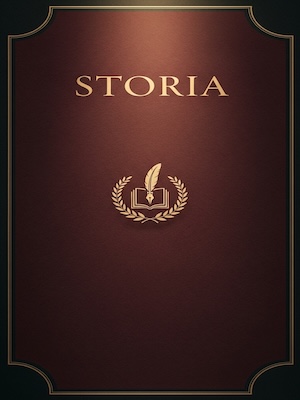第9話: ベッドの下の目撃者
俺はすぐに口を押さえ、声を出さないようにした。喉で息を止める。
その人は微動だにせず、呼吸音さえ聞こえなかった。空気だけが動いている。
冷や汗が頭皮から目に流れ、心臓が胸から飛び出しそうだった。体の中心が軽くなるほど怖かった。
外に立っているのは人か、それとも幽霊か!足の存在だけが、俺を締め付けた。
足先は俺の顔から五センチも離れていない。爪先のゴムが曇っていた。
生臭い匂いが冷たく頭頂に突き刺さる。血と泥と油の混じった匂いだった。
俺は必死にその足を見つめ、観察することで恐怖を紛らわせようとした。情報にしがみつくしかなかった。
その人は短めのゴム長靴を履いていた。サイズは大きめで、靴底には砂利と暗赤色の泥がついていた。焼却場の土か、工場の泥か。
この靴、知っている人の中で見たことがない!金田の長靴とも違う。
外に立っているのは誰なのか?人間か幽霊か?なぜベッドのそばに立っているのか!思考が円を描いて戻ってくる。
考えていると、ドアがギイと開いた。金属の軋みが細い。
足がそっと玄関側へ動いた。足音とともに油の匂いが近づいた。
しまった!夕子が帰ってきた!最悪のタイミングだ。
生死の恐怖が勝り、俺はシーツを握りしめて飛び出そうとした。人でも幽霊でも、二人なら勝ち目がある!体は無意識に戦い方を選んだ。
「やっと帰ってきたな。」金田の声だった。油の低さを帯びた声で、笑いが混じっていた。
俺は汗で背中がびっしょりになり、金田の声を聞いた途端、力が抜けて床に倒れ込んだ。膝が板に当たって痛かった。
「何しに来たの?この数日会うのを控えようって言ったでしょ?」夕子の声は硬い。扉の内側で距離を取っているのが分かった。
「会いたくてさ、へへ。昨日あんな大きなこと手伝ったんだ、今日は約束の分をもらいに来たんだよ。見返りをもらうよ。」ねっとりした声が、部屋の隅まで這ってきた。
いやらしい声に、俺はまた拳を握りしめた。爪が掌に食い込んだ。
「今は昼間よ、待てないの?」夕子の声は拒絶に満ちていた。壁を背にしている音がした。
「待てない、一刻も待てない。昼間だっていいじゃない。これからは家族になるんだし、そんなに拒まなくても……」金田は笑う。笑いが浅い。
服を脱ぐ音が聞こえてきた。布が床に落ちる擦れる音が耳を刺した。
俺は必死で耳をふさぎ、金田の卑猥な言葉と夕子の絶望的なうめき声を遮ろうとしたが、無駄だった。音は指の間から漏れた。
二人が去った後、俺は涙が止まらなかった。鼻をすする音が自分でも嫌になった。