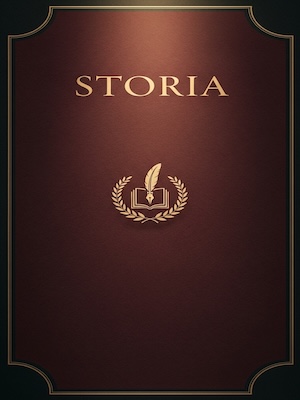第7話: 夢か現実か、消えた証拠
頭の傷の痛みも忘れ、俺は必死で夕子の職場へ走った。足音が路地に弾み、破れたビニールの端が風に鳴いた。
冷たい空気が肺に突き刺さり、氷の錐で肉をえぐられるようだった。口から吐く息が白く揺れた。
夕子にだけは何もあってはならない!その一心だけで足が動いた。
夕子は昼間、近所の小さな食堂で皿洗いをしている。油の匂いが通りまで漂っている店だ。
厨房は狭く、一目で全体が見渡せる。ステンレスの台がくもり、割れたタイルから水が染みていた。
俺は油だらけのカーテンを慌てて開けた。カーテンの端が手にべっとり貼り付いた。
夕子はいなかった!空のシンクがぬめっと光っていた。
泣きそうになった。喉が詰まって、言葉の形にならない。
夕子を失うくらいなら、取り壊しも大きな家も新しい服もいらない!頭の中で一つずつ捨てていった。
「また翔が夕子を探しに来たのかい」と、皿洗いのおばさんはあまり愛想が良くなかった。手を止めずに、声だけこっちへ投げた。
「おばさん、今日夕子は出勤しましたか?」俺は息を整えた。
「来てすぐ出ていったよ。町内会で何か図面を見に行ったとか。」おばさんはため息混じりに言った。
助かった!胸の中で硬くなっていたものが少し緩んだ。
「ありがとう、おばさん!」俺は力がみなぎった。足に血が戻っていくようだった。
「毎日タダ飯食べて恥ずかしくないのかね……」おばさんの小言は気にならなかった。今日の俺には関係のない音だった。
子供の頃から、満足に食べられない俺は、尊厳は満腹な者だけのものだと知っていた。空腹のとき、プライドは小さくなる。
遠くで、夕子が町内会の女性たちと何か話しているのが見えた。手にしているのは白い紙束だった。
女性の顔は苛立ちでいっぱいだったが、夕子はにこやかだった。笑顔の下に、眼差しだけが張り詰めていた。
俺は近づかず、家に戻った。足取りは早いのに、頭の中は重かった。
昨日のことが夢だったのか、必死に思い出そうとした。音、匂い、重さ、全部辿った。
部屋はきれいに片付けられ、寝具やボロボロの綿入り上着は外に干されていた。黒ずんでいて元の色も分からない。風に揺れるたび、乾いていく音がした。
部屋のどこにも血の跡はなかった。拭き損ねたはずの端にも、赤は見えない。
頭がまた痛み出した。町医者は、頭を怪我すると後遺症が残り、小さな問題が出るかもしれないと言っていた。額の皮膚がきゅっと縮む。
もしかしたら夢だったのか。俺はベッドに座り、頭を抱え、落ち込んだ。目を閉じても、昨日がまぶたの裏に映った。
父が生きているなら、いずれ俺たちはまた殴り殺される。あの足音が、またドアを蹴破る。
自分の手を見て、昨日洗濯でふやけた手がきれいで血もついていないことに、少しだけ安心した。爪の間も、白いままだ。
俺は横になり、父が本当に消えてくれる方法はないかと考えた。理屈のある消え方だけを探した。
この狭くてボロボロの部屋で、俺と夕子は想像通りの生活を送れるのだろうか。壁紙のない壁でも、笑える日が来るのだろうか。
大きな家に住み、肉を食べ、割引でも酸っぱくもないケーキを食べられる日が来るのだろうか。夢を現実に引っ張る糸は、まだ細い。
考えているうちに、何かがおかしいと気づいた。胸の奥で小さな針が動いた。