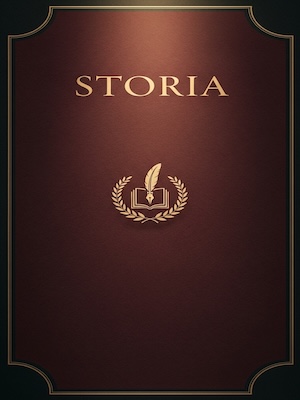第6話: ベッドの下の空白
手が震え、工場のテレビで見たように、水で床の血を拭き取った。バケツの水はすぐに赤く濁った。
毛のほとんどないブラシに冷たい水と拾った洗剤をつけて、服や寝具の血を落とした。泡がピンク色に変わり、指先がふやけた。
ストーブの血は黒く焦げ付いていた。熱の跡は、簡単には取れなかった。
焦げた鉄の匂いがした。鼻の奥に刺さって離れない匂いだった。
壁の古い時計を見ると、夕子がもうすぐ帰ってくる時間だった。針の音がやけに大きく聞こえた。
俺はビニールで父を何重にも包み、ガムテープで留め、ベッドの下に押し込んでシーツをかけた。膝と肘に力を入れて、息が切れた。
夕子が夜勤に出かけたら、遺体を捨てに行こうと思っていた。彼女の足音が角を曲がるのを待ってから。
もう考えていた。金田のスクラップ工場の産廃に紛れ込ませて、プレス機で圧縮してから産廃ルートで処理場へ送るつもりだった。深夜なら、誰も見ていない。
いつも見ていた、ショベルカーが何でもすくい上げて機械に入れ、四角い圧縮パックになってフォークリフトで運ばれていく。産廃は直接焼却場に送られるのだという。鉄と火が全てを呑み込む。
その夜、俺はとても安らかに眠った。まぶたの裏で、寒さが薄まった。
夢の中で、俺は夕子と明るくて暖かい大きな家に住んでいた。窓ガラスは複層で、風の音がしなかった。
朝食はハンバーガーで、広告のように牛肉パティとレタスが挟まっていた。紙袋のシミもない、きれいな朝だった。
夕子は白いダウンコートを着ていて、汚れ一つなかった。髪は艶があり、笑うと頬が柔らかく動いた。
俺はペンと本を持ち、学校の門で近所の人たちの優しい笑顔を見ていた。誰も俺を突き飛ばさなかった。
あまりに素晴らしい夢で、目覚めたくなかった。目が覚めるという行為そのものが、罰に思えた。
目が覚めると、もうすっかり明るくなっていた。大丈夫、夕子は昼も仕事だ。時間は俺の味方をしているように見えた。
俺は歌を口ずさみながら、ゆっくりと服を着た。袖が血で固まっていないことに安堵した。
もうすぐ、夢のような日々がやってくる。数字と図面が、本物の床に変わる。
俺たちの生活を壊そうとした人間は、俺が殺した。ベッドの下にいる。そこにあるはずだ。
俺は下を向いて、手を伸ばした。シーツの端に指を引っかける。
何もなかった!空気しか掴めない。
シーツをめくっても、白いシーツの下は影だけ。膝が抜けた。
冷や汗が一気に噴き出した。背中が一瞬にして濡れた。
俺は幽霊など信じていない。けれど、理屈が崩れると、影は全部同じ色になる。
最初に思ったのは「もしかして死んでいなかったのか?」ということだった。あり得ないはずの可能性が、最初に頭に浮かぶくらいには追い詰められていた。
もし生きていたなら、俺と夕子に復讐しに来るはずだ。刃物と怒鳴り声を持って、すぐそばまで。