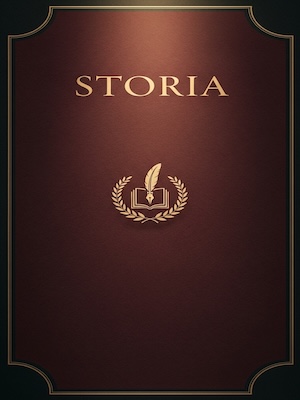第5話: ケーキとハンマーの夜
俺はハンマーで釘を打っていた。乾いた音が壁に繰り返し跳ね返った。
そのとき、またドアが蹴破られた。ビニールが破れ、冷たい風が口の中に入ってきた。
父は目を血走らせ、鋭く磨かれた包丁を持っていた。刃先が蛍光灯の光を吸っていた。
「さっさと入居承認通知を出せ!早く出せ!」唾と怒りが混ざって、言葉が床に落ちた。
この辺りの家が取り壊しになり、最低でも五百万円もらえると聞いた。補償金の支給決定の通知や見込み額の案内、公営住宅の入居承認通知があれば、俺の借金も一気に返せる!もう逃げ回る必要もない!父の頭の中は金額の計算ばかり。数字のことしか考えていない。
「じゃあ、俺と夕子はどうなるの?」俺は聞いた。声は自分でも驚くほど冷たかった。
父は俺をバカを見るような目で見た。「お前ら?関係ないだろ!」鼻で笑う音が憎らしかった。
「だったらこっちも関係ない!」俺は父の口調を真似た。喉の奥で、何かが切れた。
彼はまた俺を蹴り、腹に当たった。空気が一気に抜け、膝から力が落ちた。
俺はテーブルのケーキの上に倒れ込んだ。甘いクリームの小さなケーキだった。白い山が崩れる音がした。
明日は俺の誕生日で、そのケーキは夕子がスーパーで一時間半並んで買ってきてくれたものだった。手の甲に残った冷たさが、列の長さを語っていた。
毎週火曜日、スーパーでは賞味期限間近のケーキが九割引で売られる。火曜の冷蔵ケースは、小さな希望であふれていた。
俺は痛みで膝をつき、顔中に酸っぱくなったクリームがついた。砂糖の匂いが、吐き気と一緒に込み上げた。
父は俺の髪をつかみ、無理やり顔を上げさせ、包丁で目を指した。刃先が瞼に影を落とした。
「このクソガキ、そんな目で見るな!またそんな目で見たら、目玉をくり抜いてやる!」低い声が耳に絡みついた。
興奮と苛立ちが混じった声で、「さっさと入居承認通知を出せ!」と叫んだ。包丁が言葉の最後で小刻みに震えた。
俺は肉のついた骨、床に押し付けられた骨、嫌な金田、細目の町医者、近所の夕子への陰口、凍えた手でケーキを持ち帰る夕子の姿、テレビで見た明るくて暖かい大きな家、夕子の明るい笑顔を思い出した。胸の中で全部が一度に燃え上がった。
ハンマーはまだ俺の手の中にあった。釘の頭を打ち込むための重みが、別の用途に切り替わった。
「分かった、どこにあるか知ってる、探してくる。」俺は静かに嘘をついた。
父は俺の髪を離した。指の跡が頭皮に残った。
「分かればいいんだ。」満足げな鼻息が荒れた。
彼は嬉しそうに振り返り、壊れたケーキを手づかみで食べた。口の端にクリームが白く広がった。
俺は手にしたハンマーで、父の頭を何度も叩きつけた。音は重く、世界の音がそれに従った。
ハンマーがこんなに軽いと感じたのは初めてだった。頭に叩きつけるたび、怒りが収まらなかった。軽さは、俺の中の何かを麻痺させた。
血が俺の顔や汚れた綿入りの上着、寝具、赤く燃えるストーブ、拾ってきたプラスチック板に飛び散った。飛沫の粒が一瞬光った。
父は息絶えた。呼吸の音が途切れ、部屋の静けさが変質した。