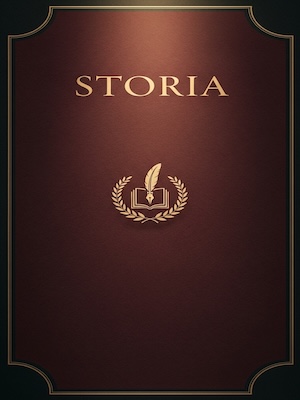第4話: 立ち退き料という希望
俺は手足を使って夕子のもとに這い寄った。「夕子、町医者のところに連れていくよ、夕子……」と必死だった。声が震えてうまく出なかった。
「翔、大丈夫よ、ここでいいから。綿の布を持ってきて縛ってくれれば大丈夫。」絞り出す声は落ち着きを装っていた。
俺は夕子の言うことをよく聞いた。手の震えを飲み込んで、引き出しをまさぐった。
慌てて綿の布を縛るころには、血が夕子のボロボロのダウンジャケットに染みていた。古い白は、黒ずんだ赤に飲まれていく。
俺は泣き出してしまった。涙が縫い目の痛みをさらに熱くした。
「翔、泣かないで、いい日が来るよ。」
夕子は俺の頭を撫でて、「この家もすぐ取り壊しになるの。さっき町内会で確かめてきたの。」と言った。声の端に、久しぶりの光が宿っていた。
取り壊しになったら立ち退き料が入る。肉が食べたいなら肉、新しい服も大きな家も買える。学校にも行ける。苦しい日々はもうすぐ終わる!夕子の言葉は、寒い部屋に火を灯した。
たった十平米の小さなバラックでも、数百万円の立ち退き料がもらえる!計算表の数字は、現実の匂いを持って迫ってきた。
俺は初めて夕子の明るい笑顔を見た。口角が上がり、目の端が柔らかくなった。
つられて俺も笑顔になった。泣き笑いの顔で、吸い込む息が少しだけ軽くなった。
昔、祖父母は父の借金を返すために家を売った。買い手は俺たちが可哀想だとバラックに住まわせてくれた。雨漏りのする屋根の下でも、彼らは俺たちに場所を残した。
その後、祖父母も亡くなり、買い手も何も言わず、家は何度も転売され、権利証にもバラックのことは記載されなかった。地図の端にも、俺たちの点は載らなかった。
それが俺と夕子の家となった。ボロでも、そこでしか眠れなかった。
朝早く、夕子はまた出かけていった。古いスニーカーの靴紐をきゅっと結び直して、振り返らずに路地へ消えた。
夕子は俺の工場の仕事を辞めさせ、俺は大人しく家で養生していた。指先はまだ鈍く、重たい物を持つと縫い目が刺すように痛んだ。
俺はゴミ捨て場からプラスチック板を拾ってきて、ドアに打ち付けようとした。割れたガラスの隙間を埋めたくて、寒さから夕子を守りたくて。