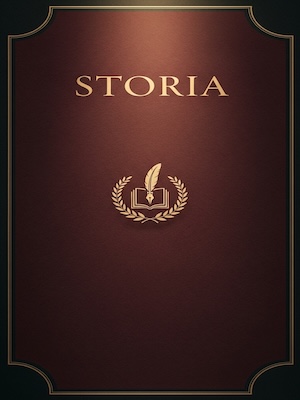第3話: 手羽元の骨と戻った鬼父
父が二度目に夕子を訪ねてきたとき、夕子は家にいなかった。通りの角で誰かと話している声が遠くに聞こえただけだ。
家にいたのは俺だけで、夕子が作ってくれた手羽元の煮込みがあった。湯気の向こうに葱が踊っていた。
とてもいい匂いだった。白い脂の輪が、静かに揺れていた。
俺は食べなかった。夕子が帰ってきたら一緒に食べようと思っていた。ひとりで美味しいものを食べる気にはなれなかった。
だが夕子は帰らず、父がドアを蹴破って入ってきた。ビニールが裂け、冷たい風が背筋を這い上がった。
「このクソガキ、あいつはいないのか?」彼は俺の名前すら知らなかった。声は空腹に苛立っていた。
「へえ、肉まで食べてるとはな!」彼は椀をつかんで、汚くすすり上げた。喉仏が上下するのが気持ち悪かった。
底には手羽元の骨が二本あり、少しだけ肉がついていた。漂う旨味の匂いが、俺の腹を刺激した。
彼は手で骨をむさぼって肉をこそげ、べちゃりと器の縁に並べると、椀をがしゃっと卓に戻した。乱暴な音が板に跳ねた。
俺は器の縁に積まれた肉のついた骨を見て、唾を飲み込んだ。喉が痛いほど乾いていた。
「知ってるか?夕子が川崎臨海部のバラック街で、再開発の補償関係の書類をどこにしまったか?」父の目は紙切れの一点を探す泥棒の目だった。
俺は床の骨を見つめて首を振った。視線を上げる勇気はなかった。
彼は俺を平手打ちした。「このクソガキ、俺が話してるんだぞ!」頬に火がついたみたいに熱が走った。
頭の傷はまだ治っていないのに、その一撃でまた血が滲んだ気がした。縫い目がずきずきと文句を言った。
「俺はお前の父親だ!この家は俺のものだ!分をわきまえろ!」吐き出される言葉が汚れていた。
俺は彼をじっと見つめて黙っていた。何も言わない沈黙が、唯一の抵抗だった。
彼はまた平手打ちした。「なんだその目は!」声は少し怖がっていた。
俺はそれでも彼を見つめていた。目の奥で何かが冷たく固まっていく。
彼は何か武器を探そうとしたが、部屋には何もなかった。細い棚の上にも、台所の隅にも、ただ生活の残りかすだけがあった。
仕方なく骨を床に押し付けて、「いつかお前ら全員殺してやる!」と吐き捨てた。骨の白さが、ひどく下品に見えた。
夕子が帰ってきて、小さな鷲のように飛びかかった。細い腕が、風を切った。
部屋のものを父に投げつけ、「出て行け!今すぐ出て行け!」と叫んだ。声は壁に跳ね返って縮んだ。
「よくも来れたな!私の父親はお前のせいで死んだんだぞ!借金取りが家に押しかけてきて、両親は財産を全部差し出した!今さら金をせびりに来るなんて!」彼女の言葉は、過去の血を引きずっていた。
「誰が差し出せと言った!俺は頼んでない!あいつらが勝手にやったんだ!」父は逆上した。
夕子は必死で父の顔を引っ掻き、父は夕子を突き飛ばした。夕子は遠くに倒れ、頭を熱いストーブにぶつけて血が出た。鉄板がじっとりと音を立てた。
父は血を見ると手を止め、「さっさと補償金をよこせ!その手続きは世帯主の俺がやるんだ、分かったな!さもないと次はお前らを殺すぞ!最後にはこの家の権利も俺のものだ!」と叫んでドアを蹴破り、ガラスが派手に割れた。破片が床に走り、冷たい風が一斉に駆け込んだ。