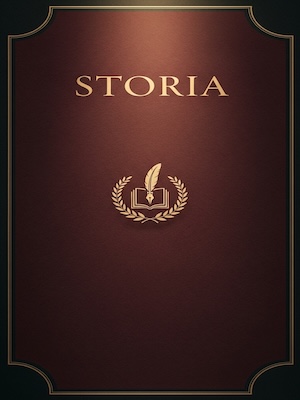第2話: 血だまりと偽りの救い手
「本当に知らないんだよ、母さんが亡くなったとき何も言わなかった!信じないなら自分で探せばいい!」夕子は必死で俺の傷口を押さえた。手のひらが血に沈み、震えていた。
血が彼女の指の間から流れ出し、どんどん慌てていった。俺は彼女の手の温度を感じて、目を閉じた。
「お願いだから、まず子供を助けて、救急車を呼んで……」彼女の声は涙に濡れていた。
「救急車?こいつが救急車なんか呼ぶ価値あるか?死んだって構わないだろ。」ぼんやりとしか顔は見えなかったが、その言葉を聞いて、胸の奥が何度もきしんだ。内側がざくざく削られるみたいだった。
これが、十数年待ち望んだ父親なのか?期待の残りかすが、その場で腐っていった。
辛い思いをするたび、家に一枚だけある父との写真を抱えて、こっそり涙を拭っていた。色褪せた笑顔の紙片に、幼い俺は何度もすがった。
夕子はそんな俺を見るたびに、「泣くな!男が泣くもんか!あいつに期待するな、もうお前なんかいらないんだよ!」と叱った。叱りながら背中をさする手は優しかった。
俺は信じていた。父はきっと遠くで一生懸命働いている。いつか必ず帰ってきて、美味しいハンバーガーや袖口から指が覗かない穴のないちゃんとした服を買ってくれて、雨漏りしない大きな家に住ませてくれると。信じていた。信じることでしか夜をやり過ごせなかった。
だが今日、俺の中の父は完全に死んだ。音もなく、冷たい水に沈むみたいに。
どんどん青ざめていく俺の顔を見て、父は慌てて逃げ出した。「保険証もないし、救急車なんて呼んだら警察沙汰になる。工場のつてで夜間も診てくれる個人医院に連れていけばいい、大したことじゃない。」玄関のビニールが風で鳴った。
寒気がして、夕子が必死で俺の名を呼んでいた。遠くに聞こえるような気がした。
しばらくして、夕子も出ていった。靴音が急ぎ足で細い路地へ消えた。
俺は死ぬのだろうか?天井のしみを数えるのが、急に怖くなった。
十分ほどして、金田がやってきた。体から油の匂いを引きずって、鼻息荒く入ってきた。
「おいおい、このクソ野郎、加減を知らないな!これ、助かるのか?」金田は俺の顔を覗き込み、息が酒臭かった。
「助かる、助かる、ただの外傷だ。病院で縫えば大丈夫。」と、金田は勝手に言って自分を安心させるように頷いた。言葉の端が震えていた。
「病院?俺にそんな金はないぞ。」金田はぶつぶつ言いながら、俺の古びたベッドの板を外した。釘が悲鳴を上げる。
「保険証もないし、救急車呼ぶと警察が来るから、近所の個人医院に運ぶぞ。工場のつてで元看護師が縫ってくれるからな。これで十分だ。」金田は肩をすくめた。
その町医者は、いつも細目で夕子を見ている年寄りだった。診療所と呼ぶにはみすぼらしい部屋で、薬瓶のラベルは黄ばんでいた。
みんな彼を胡散臭いと言い、夕子も彼の話になると必ず「ちっ、人の不幸で飯を食う汚らしいやつ」と吐き捨てていた。目の端に憎しみが宿った。
今回は吐き捨てることもなく、金田と一緒に俺をベッド板に乗せながら「ありがとう、ありがとう……」と繰り返していた。彼女の手は冷たく、必死だった。
俺は運が良かったのか、生き延びた。縫い目が額に引き攣るたびに、生きている痛みが確かになった。
夕子は毎日昼間は俺のそばで看病し、夜は隣の部屋で寝ていた。古いカーテン一枚隔てただけの隣から、彼女の寝返りの音が聞こえた。
「翔、怖がらなくていい、夕子はすぐ隣にいるから、何かあったら呼んでね」と言っていた。囁くみたいに優しく。
俺は一度も呼ばなかった。夕子もきっと疲れていると思ったからだ。彼女の目の下の影を、これ以上濃くしたくなかった。
退院の日、町医者はまた細目で夕子を見て、彼女の腰に手を触れて笑った。肩を不快に叩く仕草をして、笑った口元には歯垢が見えた。
夕子は体を強張らせ、俺の手を引いてその場を離れた。外の空気は冷たいのに、背中に汗が流れた。