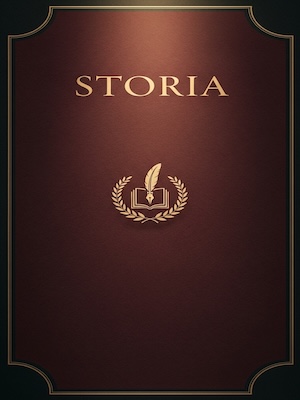第11話: 叔母の告白と四百万円
翔は私が幼いころから育ててきた子だ。手の中の温度で、季節を一つずつ越えてきた。
あの頃、私はまだ若く、子供の育て方も分からなかったし、貧しかった。子供が道を踏み外したのは全部私のせいだ。逃げずに言えるのは、それだけだ。
私がもっと時間を作って世話をし、もっとお金を稼いで学校に通わせていれば、こんなことにはならなかった。分かっているのに、そうできなかった過去が重い。
警察の方、彼に一度だけ会わせてください。何か渡したいんです。自首するまで、彼の14歳の誕生日も祝ってやれなかった。小さなケーキすら渡せなかった。
乾いた目からは一滴の涙も出ず、私は手で顔を覆った。涙が枯れるほど泣いた後は、ただ熱だけが残る。
14歳の誕生日という言葉を聞いて、向かいの年配刑事はタバコを消した。灰皿に落ちる音が短く鳴った。
「その日の出来事を話してください。」声は穏やかだったが、急かしてはいなかった。
4月14日の夜、私は仕事から帰宅した。手の甲は荒れて、指の腹はふやけていた。
部屋には強い血とカビの匂いが漂っていた。服や寝具は洗って外に干されていた。風が冷たく、布が固くなる季節だった。
翔の頭の傷がまだ治っていないと思い、特に気にしなかった。血の匂いには慣れてしまっていた。
片付けて食事をし、寝た。いつものように、電気を落として、ストーブを弱くした。
夜中、トイレに起きて靴を履かずに歩いたら、足元がベタベタした。床に足裏が貼り付く感触が、嫌な予感を連れてきた。
懐中電灯で照らすと、大きな暗赤色の血溜まりだった。光が吸われて、周りだけが明るくなった。
私は翔のものだと思い、駆け寄って揺り動かした。肩が熱く、汗の匂いがした。
翔の体はとても熱く、頭に出血はなかったが、口の中で「夕子、いい日が来るよ……剛造はもう邪魔しない、ベッドの下に……」とうわごとを言っていた。言葉は夢の中を漂っていた。
私は懸命に自分を落ち着かせ、懐中電灯で血の跡をベッドの下までたどった。光の線をまっすぐに伸ばした。
そこで人生で一番恐ろしい光景を目にした。体が勝手に冷えた。
ビニールで包まれ、血が滲み出ている人間がいた!ビニールの折り目に、赤が挟まっていた。
私は恐怖で翔のベッドに飛び乗った。ベッドの上が唯一の高台に思えた。
ベッド板がギシリと鳴り、まるで下のものが喋ったかのようだった!音が言葉のように聞こえた。
私は必死で翔を揺り動かした。「翔、起きて!翔!」声が裏返った。
だが翔は高熱で意識が朦朧とし、「剛造を殺した、俺が剛造を殺した……」とうわごとを繰り返した。言葉だけが空に浮かんだ。
私は自分を抱きしめ、冷静になろうとした。腕で自分を固めないと、崩れそうだった。
懐中電灯がテーブルに当たり、そこには朝町内会でもらった資料と、市の職員が出した再開発の政策、概算では四百〜六百万円の補償見込みがあった。数字は現実の温度を持っていた。
四百万円だよ、私の人生で見たこともない大金だ!ゼロの数に、指が震えた。
そうだ、私たちのいい日々はもう目の前、唯一の厄介者・剛造も死んだ。悪夢の種が、やっと抜けるはずだった。
私はたくさん考えた。一方はすぐに手に入る立ち退き料、もう一方はとっくに死ぬべきだった剛造。結論は一つだった。迷う余地はなかった――冷酷な計算が頭を支配した。