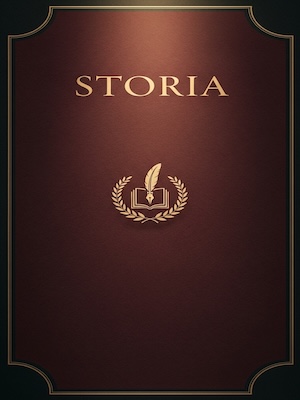第10話: 14歳未満の殺人者?
「つまり、お前の言い分は、殺したのはお前で、夕子と金田が一緒に遺体を処理した、ということだな?」取り調べ室の机越しに、年配の刑事の低い声が落ちた。言葉は淡々としているのに、刃のように鋭い。
椅子がきしむ。長時間の取調室のライトで、俺は刑事の顔がよく見えなくなっていた。白い光が輪郭を消していた。
「はい、俺が殺しました。」俺は両手を握りしめ、もう一度強調した。言葉にしないと、事実が浮いてしまいそうだった。
「2003年4月14日、夕子と住んでいたあの部屋で、俺はハンマーで父の頭を潰し、ビニールで遺体を包み、ガムテープで巻いてベッドの下に置きました。遺体の移動については知りません。ベッドの下に置いたら消えていました。」順番を崩さずに、記憶を並べた。
「なぜ今ごろ自首した?もう一か月経っているぞ?」若い刑事が眉を寄せた。ペン先が紙に触れたまま止まる。
紙が擦れる音がする。夕子は「立ち退き料が入るまで待とう」と言った。数日前に立ち退き料が入った。金の音が、ようやく現実になったからだ。
「凶器、つまり殺人に使ったハンマーは?」若い刑事の声は機械的だった。
「目覚めたらもうなかったので、分かりません。夕子が一緒に処理したのかも。」俺は視線を落とした。床の模様がやけに複雑に見えた。
「うん、問題なければ署名ね。」若い刑事が調書を読み上げ、俺にサインを求めた。押印は不要だが、指紋は後で採ると付け加えた。
指が冷えた。署名を終え、ペンを置く直前、俺は不安になって聞いた。喉の奥がきゅっと縮んだ。
「刑事さん、もし俺が当時14歳未満なら、刑事責任能力ないですよね?罪を認めて協力すれば、刑務所にも入らなくていいんですよね?」言葉が一気に出て、最後だけがかすれた。
若い刑事は調書を見た。数字の列に目を走らせる。
「当時14歳未満だったのか?」視線が少しだけ上がった。
「はい、あの日は誕生日の前日でした。今は14歳になったばかりです。」俺は結果を求めて焦った。生き延びるための理屈が欲しかった。
年配の刑事は考え込むように取調室のライトのスイッチに手をかけ、しばらく押さなかった。指先の動きだけが静かに揺れた。
「堂島刑事、この事件は明白ですし、自首もしています。証拠が揃えばすぐに解決でき、上にも説明できます。」若い刑事・小堀が言った。声は急ぎ気味だった。
「本当に明白か?」堂島刑事は何か違和感を覚えていた。この事件はそう単純ではない。言葉の間に、疑いが息をしていた。
「証拠集めは大変かもしれませんが、先月家が取り壊されたばかりですし。」若い刑事・小堀が言った。紙の端を指で整えながら。
堂島刑事は返事をしなかった。視線は机の上のどこか、見えない一点に固定されていた。
小堀はまた「上も理解してくれるでしょう」と言った。空気だけが返事をした。
真木村翔が自首した翌日、地元紙は一面トップで「バラック街の取り壊し、500万円の立ち退き料目当てに息子が父親をハンマーで撲殺!」という記事を掲載した。太い活字が、紙面の隅まで黒かった。
わずか数行だったが、目を引く見出しで新聞は即日完売した。売店の前に小さな列ができ、夕方にはもう補充されなかった。
上層部は情報漏洩を叱責し、市の再開発担当課から県警本部へ問い合わせが入り、県警から所轄へ進捗の督促・情報照会があった。受話器の向こうの声は、妙に丁寧で急いでいた。
今や事件の影響は大きく、警察は早期の解決を求められ、週次で進捗報告を求められる。期限の数字が現場に重く乗った。
だが、今日の真木村翔の供述を見る限り、まだ多くの問題が残っていた。穴の形が、初めよりも大きく見えた。
堂島刑事は、翔が4月14日時点で本当に14歳未満だったことを示す身分証を手に、その背の高さ――170センチを超えるような体格を思い浮かべ、深い疑念を抱いた。書類上の数字が、目の前の現実と噛み合わない。
翔は本当に14歳未満なのか?問いは、机の上で静かな影になった。
「小堀、翔の生年月日を確認して、夕子を再度取り調べろ。」堂島刑事の声は低く、揺れなかった。