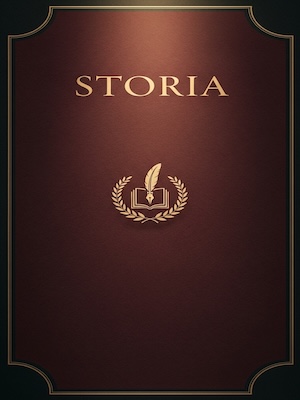第1話: 父殺しと消えた遺体
真木村夕子が金田にベッドの上で無理やり押さえつけられている間、俺はベッドの下で昨日父親を殺したときに飛び散った血痕を拭き取っていた。薄暗い一間、トタン屋根を打つ雨音とストーブの鉄の匂いが混じり合い、川崎臨海の湿った空気が肌にまとわりつく。上からスプリングの軋む音が響くたび、俺は指先に力を込めて、雑巾に染みた赤い色を少しでも薄くしようとした。
どうして遺体がベッドの下から忽然と消えてしまったのか、俺にはどうしても理解できなかった。あの重み、ビニールの感触、ガムテープの粘りまで、はっきり覚えているのに、そこには何もない。冷えが腹の奥を這いまわり、考えがぐしゃっと潰れていく感じだった。
俺は臨港警察署に自首した。油と潮の匂いが漂う埠頭近くの所轄。白い蛍光灯の光は無機質で、受付の足元のゴムマットが妙に黒光りして見えた。自動ドアの開閉音のあと、自分の足音すら聞きたくなくなった。
「親子による父親殺し」という報道が世間に広まり、事件は誰もが知ることとなった。昼のワイドショーが見出しを繰り返し、地元紙の夕刊は売店で争うように消え、工場の昼休みにまで噂話が鉄粉に混じって飛び交った。
そのとき夕子は突然供述を翻し、「殺したのは私だ、翔に罪をかぶせようとしただけ」と言い出した。泣きも笑いもしない声で、喉だけが震えていた。捜査員のボールペンが一瞬止まり、静けさが部屋に降りた。
だが金田は、俺が父親を殺したときに使ったハンマーを差し出した。油で曇った金属の先に、乾ききらない暗赤がこびりついていた。金田はニヤつきもせず、「これだ」と低く言った。
俺は幼いころから夕子と二人きりで暮らしてきた。両親は離婚し、父は「仕事を探しに行く」と言い残して、そのまま行方不明になった。行方のない靴音は、俺たちの生活の中から音を奪っていった。
夕子は父の妹だ。戸籍上は叔母だが、俺にとっては母だった。
祖母も俺が三歳のときに亡くなった。葬式の線香の匂いだけが、ぼんやりした記憶の端に残っている。
夕子だけが俺の唯一の家族だった。薄い肩に、冬も夏も俺の重さを載せてくれた。
当時、夕子はまだ十八歳で、俺のせいで一生結婚しなかった。彼女はその言葉を口にこそしなかったが、夜に独りで起きて台所でため息を吐く背中が、全部物語っていた。
大きな子供が小さな子供を引っ張って、俺たちはそうやって育った。子供なのに親の役目を半分背負っていた彼女に、俺はしがみついて歩いた。
夕子は俺を恨んでいた。自分の人生を台無しにしたと。恨みと愛情の両方で、彼女は俺を見ていた。
夕子はよく俺を殴った。殴った後で泣きながら俺を抱きしめて、「翔、お前は私の世界で最後の親族なんだよ」と言った。頬を叩いた手は同じ手で、乱暴な温度のまま髪を撫でてくれた。
俺は金田スクラップ工場で働いていた。社長は四十過ぎで、太っていてだらしない男だった。錆色の粉が舞い、油の海を長靴で踏み、昼でも暗い作業場で、俺の指先はいつも黒かった。
彼はよく俺たち親子に食べ物や小銭を渡してくれた。そのたびに夕子は工場の薄汚い一室に入っていった。ベニヤ板の壁越しに、笑い声と何かを押し殺すような音が聞こえた。
出てくると、夕子の目は赤くなっていて、体にはいつまでも治らない傷があった。袖の中に隠した痣は、洗っても消えなかった。
俺の十四歳の誕生日の数日前、父・剛造が帰ってきた。足音は乱暴で、ドアを蹴る音は、近所の犬を黙らせた。
彼はひどい臭いがした。金田よりも臭かった。酒と汗と古いタバコと、外で染み付いた煤けた匂いがまとわりついていた。
父は夕子を床に押し倒し、腹を蹴りつけた。「出せ!同意書を出せ!ハンコ押したあの書類だ、早く出せ!」と吐き捨てる声に唾が飛んだ。
俺は止めに入ったが、力では敵わず、父の腕に思い切り噛みついた。嫌な皮の味が舌に残った。
父は修理用のスパナを手に取り、俺の頭を殴った。鈍い音がして、視界が白く跳ねた。
「このクソガキ、俺に噛みつきやがって!誰が親父か分かってないのか?」怒鳴り声は近すぎて、耳が痛かった。
血が目を覆った。世界は赤い膜の向こうに滲んだ。
死んだ魚のようだった夕子が、俺をかばって飛びかかった。あの細い体が、音を立てて父にぶつかった。
「子供を殴らないで!何も知らないんだから!」声は掠れているのに、真っ直ぐだった。
夕子の体は、俺の知っている誰よりもいい匂いがした。石鹸と安い柔軟剤、それでも俺にとっては安心の匂いだった。
血が俺の目に流れ込み、温かく流れ出た。頬を伝い、口の端まで鉄の味が広がる。
「父」と名乗るその男は、スパナで夕子を指し、「あいつを生かしておきたければ、さっさと年寄り二人分の手続きの書類を出せ!」と叫んだ。祖父母の名残の紙切れが、彼には金にしか見えていない。