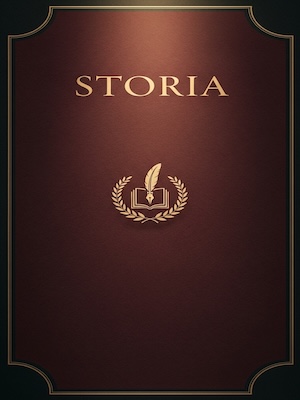第6話:再会トイレと静かな別れ
それ以降、陸は私の前に現れなくなった。彼は会社を辞めて別の会社に行き、私は支社長に就任した。常務からの異動で、キャリアの流れも自然だった。再会したのは、二年後のビジネスパーティーだった。
彼は暗い色のスーツを着て、以前より痩せ、頬がこけ、肌はさらに白く、青い静脈が透けて見え、どこか病的だった。死んだような目が、私を見た瞬間だけ、あの冬の雪夜のように輝いた。私はワイングラスを持って彼の肩をすり抜け、後ろの重役たちと談笑した。その間ずっと、背中に彼の視線が刺さっていた。
宴も半ば、私はトイレに立った。トイレの照明は故障していて、薄暗く、時々ちらついていた。私は洗面台で手を洗い、顔を上げると、陸が鏡越しに立っていた。彼は私の背後に立ち、じっとした視線を鏡に落とし、私と目が合った。私はうつむき、紙で手を拭き、宴会場に戻ろうとした。
その瞬間、照明が「ジリッ」と音を立てて消え、トイレは真っ暗になった。
真っ暗。
息が詰まる。
「怖がらないで、俺がいるよ。」彼は私の手首を引き寄せ、抱きしめて、小さな声で優しく慰めた。私は暗闇が怖い。子どもの頃から寝る時は常夜灯が欠かせなかった。同棲し始めた頃、彼はそれに慣れず、夜眠れずに目を赤くしていた。
でも彼は私に合わせるのではなく、私をぎゅっと抱きしめ、自分の頭を私の首元に埋めて、私を暗闇から守るようにした。港区の部屋の暗がりを、彼の体温がやわらげてくれた。今、二年ぶりにまた彼に抱きしめられていた。
灯りが戻る。
私は彼を突き放し、よそよそしく礼儀正しく言った。
「久しぶりだね、陸。」
「久しぶり。」彼は目を赤くし、喉を鳴らし、かすれた声で言った。「大和、この二年、元気だった?」私はうなずき、彼の目尻の涙を拭った。
「元気だよ。」
「それならよかった。」彼はぎこちなく笑い、「君が幸せなら、それでいい。」私はこれ以上トイレで立ち止まりたくなくて、彼の震える肩を軽く叩き、廊下へ向かった。去り際、私は小さな声を聞いた。
「大和、会いたかったよ。」私は足を止め、振り返る衝動を抑え、その場を離れた。廊下の端で振り返り、トイレの方を見やり、静かに言った。「陸、さようなら。」