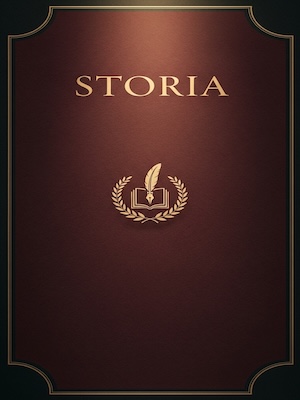第3話:電話越しの別れと雪の夜
「なんで電話に出ないんだ?指輪をテーブルに置きっぱなしにして、どういう意味だよ?別れたいのか?」彼の声は歯ぎしりするような怒りに満ちていて、どこかに悲しみも混じっていた。
私は彼の詰問を遮り、眉間を押さえながら切り出した。「陸、君がネットに書いた投稿、見たよ。」彼はすぐに黙り込み、次に口を開いた時には声が弱々しかった。
「どの投稿?何のこと?よくわからない。」
「思い出させてあげようか?」私は軽く笑い、投稿の内容をそのまま読み上げた。「年上で束縛強いし、細かくて、すぐセックスしようって言ってくる……」
彼は喉を詰まらせ、何か言い訳しようとしたが、長い沈黙の後も何も言えなかった。私は静かにため息をついた。
「陸、そんなに私が嫌いなら、もっと早く言ってくれればよかったのに。私は君に執着しているわけじゃない。」彼は大きく息を吸い込んだ。
「どういう意味だ?」
私は胸に手を当て、こみ上げる苦しさを抑えた。「陸、別れよう。」
「君が俺と別れるの?」彼は信じられない様子で、声を荒げた。「十年我慢してもこの言葉を口にしなかったのに、なんで最後に言うのが君なんだよ!」彼は子どものように、どうでもいいことにこだわる。でも今回は、私はもう以前みたいに彼のわがままを許さなかった。
「週末までに出て行って。帰宅した時に、もう君の姿を見たくない。」私は電話を切り、服を着てホテルを出た。
道端で年配の店主が小さな売店の蒸籠から肉まんを売っていた。私は一つ買い、食べ終わると紙を持ったまま、見知らぬ街を一人で歩いた。
札幌はもう冬。風が吹くと、数片の雪が舞い落ちてきた。私は顔を上げて目を細め、頭上のちらつく街灯を見上げた。なぜか、陸のことを思い出した。
2016年、私たちが付き合って二年目。あの冬は特に寒く、雪が何度も降った。私は昇進のために忙しく、毎日遅くまで働いていた。彼が初めて会社に迎えに来たのも、雪の夜だった。痩せた少年が一人、街灯の下に立ち、傘もささず、真っ白なカシミヤのマフラーを巻き、凍えた鼻先を赤くしながら、金色に染まる雪を頭に積もらせていた。
あの頃の彼は幼く、純粋で、少し小賢しいところも、雨に濡れた子犬のように可愛らしかった。私は彼より七歳年上で、幼い頃から虚飾の世界で生きてきた。港区の“世間体”に晒されることにも慣れていた。彼の拙い演技が私に通じるはずもなかった。
私は自ら進んで彼の罠に落ち、野心的な狼の子を手懐けようとした。あの時私は二十五歳、若気の至りで自信に満ちていた。今や十年が過ぎ、私は疲れ果て、この恋に惨敗した。
夜、ホテルに戻り、バスタブに浸かって夜景を眺めながら眠気に襲われた。陸からまた電話がかかってきた。
「なんで帰ってこないんだ、俺を避けてるのか?最初付き合った時、俺が半年以上も追いかけて、君はうなずいてくれたのに。今になって別れたいなんて、俺は食事も喉を通らず眠れないのに、君はたった二言で終わりかよ、どうして?」
彼は酒を飲んでいるようで、同じ言葉を何度も繰り返した。
「これは二人の問題なのに、どうして決定権は全部君にあるんだ?大和、会いたい、面と向かって話そう!君は全然怒ってないのか、俺のこと罵りたくもないのか?」
私は黙った。
私は彼の声を聞きながら、目がしみて喉が詰まり、しばらくしてやっと名前を呼んだ。
「陸。」私は力なく頭を仰け反らせ、体を冷たい水の中に沈めた。「もうやめてくれ、疲れた、寝たいんだ。」
彼の感情がまた爆発した。
「またそれだ、またそれだ、喧嘩のたびに君はそうだよ、『やめて』『静かに』『水飲んで落ち着いて』って、いつも上から目線だ。君は悲しくも怒りもしないのか?死人みたいに生きてて楽しいのか?」
私は彼の怒りの訴えを聞きながら、手の甲で熱い目を覆い、心臓がぎゅっと痛んだ。
「ヒステリックにならなきゃ、愛してるって証明できないのか?泣き叫ばなきゃ、悲しいって伝わらないのか?陸、俺たちはもう大人だ。ただの別れだ、きちんと終わろう。」
彼はしばらく沈黙し、再び出した声は嗚咽混じりだった。
「きちんとなんてしたくない、ただ会いたい。帰ってきたら、会ってくれる?大和さん。」私は答えず、電話を切り、彼を着信拒否に設定した。