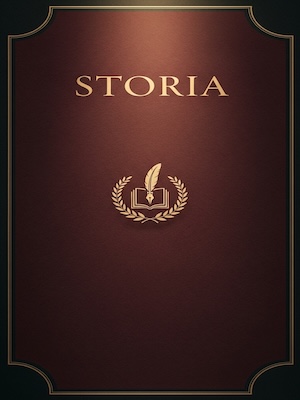第1話:十年目の裏アカ暴露
私の恋人は子どもっぽくて、いつも私を悲しくさせる。彼が十八で私と付き合い出したから、ずっと年下だ。だから私は甘やかしてきた――年の差だし仕方ないって自分に言い聞かせて、拙いわがままも泣き顔も、抱きしめて受け止めてきた。
十周年の今夜、彼がシャワーを浴びている間、私はふとある裏アカの投稿を見つけた。東京・湾岸エリアの高層マンション。夜景の光がガラスに流れて、湯気が寝室の空気を少し曇らせている。投稿内容はシンプルで、全編がパートナーへの愚痴だった。
「今カレと一緒に十年。年上だし、束縛強いし、生活の細かいことまでうるさい。一番イヤなのは、すぐにセックスしようって言ってくるとこ。でも俺、ノンケだし、彼には全然欲湧かない。最初に付き合ったのも、ただステータス上げたかっただけ。男の……正直無理……」
私は一行ずつ読み進めるうちに、心がじわじわ冷えていった。そして、その投稿の位置情報タグと、添えられた写真の窓枠が見覚えあるものだと気づいた瞬間――
……え?
まさか。
胃がきゅっと縮む。
私は確信した。投稿主は、私の恋人だ。偶然なんかじゃない。時間も、口ぶりも、全部が彼を指していた。
彼は元々冷淡な性格で、何かに飽きると特に言葉が辛辣になる。それが彼の悪い癖だって、私はずっと知っていた。若さで済ませられるうちは目をつぶってきた。でも、いつかその一面が鋭い刃になって、私に向けられる日が来るなんて思わなかった。
今日は、私たちが一緒になって十年目の日だ。私は出張先から急いで戻り、彼とキャンドルディナーを共にした。湾岸のマンションのダイニングはバラで飾られて、花畑みたいに華やいでいた。彼は片膝をつき、自分の手で私の指に指輪をはめてくれた。その眼差しは優しくて、誓いの言葉も真摯で、全部が嘘とは思えなかった。区のパートナーシップ宣誓についても、最近ずっと二人で調べていた。世間体だって、乗り越えるつもりだった。
私は諦めきれず、投稿の時間を確認した。十時半過ぎ。その頃、私たちは情熱的なキスを終えたばかりだった。彼は私を膝に乗せ、顎を私の肩に預けたまま、スマホで文字を打っていた。私は息を切らせながら彼の髪にキスして、わざとからかった。「こんな時までスマホいじって、そんなに依存してるの?」彼は聞き終えるとスマホを脇に投げ、私の耳たぶに軽く噛みついた。
「どの国のチャペルが一番綺麗か調べてたんだよ!」
その口調には、ちょっと拗ねた響きがあった。演技が上手いな。笑いそうになったのに、喉が固まって声にならない。口元だけが動いて、音は出なかった。指先の熱は胸の冷えに触れても、弾けずに消えた。
「何見てるの?」間宮陸がバスルームから出てきて、上半身裸のままベッドに飛び込んできて、私を抱きしめた。暖かく湿った息が私を包む。前なら安心できたのに、今はただ息苦しい。私は画面を消し、彼の視線を遮った。
「何でもない、仕事だよ。」彼は特に気にせず、軽く鼻歌を歌いながら私の額に額を寄せてきた。半乾きの髪がカールしていて、水滴がまだ落ちている。その水が私の目に入り、しみて痛かった。私は彼を押しのけた。
「どいて。」彼は私の様子が違うことに気づき、顔を上げて指先で私の目尻を撫でた。
「どうして赤いの?」私は彼の髪先を見やりながら答えた。「水が目に入っただけ。」彼は困った顔をして、私の上から飛び降り、バスルームに戻っていった。中からドライヤーの音が聞こえる。窓の外の海風がガラスを撫でる音まで、いつもより冷たく響いた。
スマホに通知が入り、投稿が更新されていた。
「年上の男ってさ、毎日毎日、なんであんなにわがままなんだ。目尻にシワまでできて、泣いたって誰も同情しないくせに、いつも俺に機嫌悪そうな顔ばっかりしてる。本当に扱いづらい。」
私はバスルームを振り返った。すりガラス越しに光と影が揺れ、彼の細いシルエットが映る。ドライヤーを当てながらスマホをいじっていた。乾いた風が髪を揺らし、その向こうで青白い画面がちらりと光る。私の全身から血の気が引いていく。
私たちが一緒にいる間中、彼は私にうんざりしていたのだ。十年という時間は、彼にとっては重すぎて、私にとっては甘すぎたのかもしれない。どちらにせよ、終わりの形は残酷だった。
彼が髪を乾かして戻る頃には、私はもうベッドで横になっていた。彼は布団をめくり、背後から私をきつく抱きしめ、体をぴったりと密着させてきた。熱い息が私のうなじにかかり、諦めたような口調で言う。
「ねえ、俺、何か怒らせることした?」
「なんでまた機嫌悪いの?」私は黙ったまま目を開け、窓の外の漆黒の夜を見つめて言った。「何もないよ。ただ疲れてるだけ。契約もまだ決まってないし、明日の朝は札幌に飛ばないといけないから。」彼は少し不満そうに、私の首筋にキスを落とした。
「じゃあ帰ってきたら、埋め合わせしてよね。」彼の甘えたような口調を聞きながら、私は投稿の中のあの二行を思い出していた。
「俺は彼に全く欲情しない。男の……正直無理……」
指輪が指に触れるたび、その言葉が中に刺さって疼いた。
彼が十八歳で私と付き合い始めた頃、初めての恋で、まるで子犬みたいにまとわりついてきた。四六時中、私の首筋に噛みつきたがって、ベッドでじゃれ合っていた。あの頃、私は彼に振り回されてばかりで、拒もうとしてもできなかった。彼の瞳は本当に綺麗で、そこには私しか映っていなかった。私は十八歳の陸を拒むことができなかった。
でも、十八歳の陸は、私を愛していなかったのかもしれない。あの熱は、ただの飢えと野心からくる興奮で、私への愛ではなかった――そう思った途端、胸の奥の炎が音もなく消えた。
翌朝、まだ暗いうちに私は起きた。陸は物音で目を覚まし、私が洗面している間に、キッチンで軽くうどんを作ってくれた。潮の匂いのする窓際のテーブルに湯気が立ちのぼった。私が食卓につくと、彼はあくびをしながら部屋に戻ってまた寝てしまった。
私はそのうどんを食べず、ただ一人でテーブルに座っていた。長い間、座ったままだった。昨夜のキャンドルとバラはまだ片付けられていなかった。キャンドルはとっくに消え、蝋だけが高低差をつけて燭台に垂れていた。枯れたバラの花びらは、灯りが消えた今、乾いて黄ばんだ色を晒していた。ロマンチックな雰囲気は消え去り、残ったのは散らかった部屋だけだった。
私は指輪を外し、すっかり冷めきったうどんの隣に置いた。そして立ち上がり、ここを去った。何も告げず、十年の部屋から視線を外し、扉を閉めた。